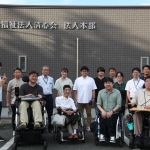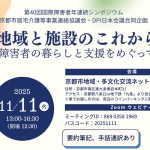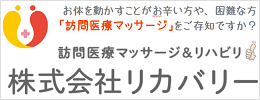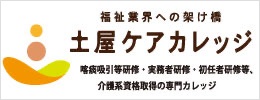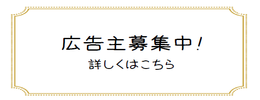8月7日(木)社会福祉法人清心会 視察レポート①-40年以上にわたり取り組んできた地域福祉と地域移行支援の実践-
2025年08月29日 地域生活雇用労働、所得保障障害者権利条約の完全実施

写真:西部秩父駅の前の”CHICHIBU”と書かれたモニュメントの前で
2025年8月7日、埼玉県秩父市にある社会福祉法人清心会をSTEPえどがわの今村さん(DPI事務局次長)、中曽根鈴音さん、CILふちゅうの岡本さん(DPI常任委員)、DPI日本会議の崔、白井、笠柳で訪問することが出来ました。
DPI日本会議はキリン福祉財団からご助成いただき、今年度から「障害者権利条約の次回審査に向けた脱施設・インクルーシブ教育推進プロジェクト」に取り組んでいます。
この視察は脱施設・脱病院、地域移行に関する先駆的な取り組みを行っている自治体や、施設などの視察を通じて、将来的なモデル事業の提案や実施につなげていくとともに、脱施設の政策づくりに取り組む団体のネットワークづくりの一環として実施しているものです。
社会福祉法人清心会は、埼玉県秩父地域に拠点を置き、1980年代から「すべての人が地域で暮らせる社会」を目指して福祉事業に取り組んできた法人です。法人理念には、「誰もが地域の中でその人らしく、幸せを感じながら機嫌よく暮らせる共生社会をめざす」と掲げています。
事業は通所・入所・グループホーム・相談支援など幅広く展開されており、現在では利用者約900名、職員約340名が関わる大きなネットワークへと成長しています。福祉サービスにとどまらず、アート活動や地域行事への参加を通じて、一人ひとりの「その人らしさ」が地域の中で輝くような支援が行われています。
また、「一日一笑(One day One smile)」を大切に、笑顔のある暮らしと、人と人とのあたたかなつながりを重視しています。清心会は、障害のある人もない人も、共に支え合いながら安心して暮らせる地域づくりを進めています。

写真:駅までリフトカーでお迎えに来てくださいました

写真:最初に訪問した「さやかサポートセンター」の建物
地域は終の住処ではなく、新たな暮らしの出発点 ― 岡部さんが語る地域福祉の理念
最初に岡部浩之理事長より、地域福祉に関するお話をいただきました。清心会では、「すべての人が地域で暮らせる」という理念のもと、40年以上にわたり地域移行支援や地域とのつながりづくりに取り組んでこられました。


写真 左:お話をしてくださっている岡部さん / 右:真剣に話を聞いている私たち
岡部さんはまず、地域は「終の住処」ではなく、「新たな暮らしのスタート地点」であるという考え方を強調されました。入所施設で問題行動とされていた方が、地域のグループホームで穏やかに暮らすようになった例も多く見られるそうです。
例えば、施設ではテレビを壊してしまったり、冷蔵庫の中のものを勝手に食べてしまったりしていた方が、地域に出るとそうした行動をしなくなることがあるとのことでした。これは、環境が人に与える影響の大きさを示すものです。
一方で、施設では問題がなかった方が、地域での生活を通じて自我が芽生え、支援が新たに必要となるケースもあるそうです。岡部さんは、そのような変化を丁寧に受けとめ、誰一人として「路頭に迷わせない」ことを大切にしているとお話しくださいました。
清心会では、アパートを一棟借り上げた「アパート型」や、より一般的な住宅に近い「サテライト型」など、さまざまな形態のグループホームを運営しています。知的障害のある方を中心に始まった取り組みですが、現在では精神障害や高齢に伴う身体障害を持つ方など、より多様な方々を対象としています。
また、食の提供を通じた工夫も大変印象的でした。かつて昼食に関する苦情があったことから、「選べるカレー」の提供を始め、社員食堂や学食のように自分で選べるスタイルを導入したそうです。カレーはB型事業所で製造され、年間300万円を売り上げるまでに成長しました。
西武ホテルの撤退により元シェフを雇用する機会にも恵まれ、さらに質の高い食事の提供が可能となったとのことです。また、セントラルキッチンを活用し、職員の負担軽減も実現しています。
清心会では、「60点でいい、100点は目指さない」という言葉を大切にしており、無理をせず、続けられる形で支援を積み重ねてきたということです。
岡部さんは、「無いものは無い。ならば作ればいい」という逆転の発想を大切にされており、地域に必要な支援や仕組みをゼロから構築する力と柔軟な発想が随所に感じられました。また、利用者に寄り添い、生活全体を支えることの重要性を繰り返し伝えてくださいました。
お話の後に、主にレスパイトケアで使用している建物の中を見せていただきました。


写真 左:居間の様子 / 右:居間にいる今村


写真 左:お風呂 / 右:トイレの様子
さやかワークセンタ―
続いて、さやかワークセンタ―を見学させていただきました。ここは障害のある方々が自分の力を活かしながら働くことを目指す通所型の福祉施設です。パンやラスクの製造・販売をはじめとした作業を通して、地域社会とのつながりを深めながら、自立した生活の実現を支援しています。


写真 左:清心会のアンバサダーでもあり、利用者でもある方から、作っているラスクについての説明、試食もさせていただきました。ニコニコしながら、嬉しそうにお話しされているのがとても印象的でした / 右:様々な味のラスク、とても美味しかったです。
ここではベーカリー部門と生活介護部門の二つの柱があり、ベーカリー部門では、本格的な製パン設備を活用し、利用者が生地づくりから袋詰め、販売までを一貫して行っています。
一方、生活介護部門では、軽作業やレクリエーション、創作活動を通して、無理なく日中を過ごせる環境が整えられています。1日のスケジュールは、朝の会から始まり、午前・午後の活動、昼食、そして終わりの会を経て、16時には終了となります。
活動内容は利用者の特性や希望に応じて柔軟に調整されており、「働くこと」と「心地よく過ごすこと」のバランスが大切にされているということです。


写真:さやかワークセンターの中にある味噌工房も見学させていただきました
その後、併設されているのぞみ工房を見させていただきました。さやかワークセンターで作ったパンやみそなどを販売されています。

写真:お店の中の様子


写真左:お店の外観 / 右:購入した甘味噌とチキン照り焼きマヨパン(マヨラーにはたまりません)
視察報告パート2では、芸術や文化を軸にした「アーティストテラス634」の取り組みや、入所施設の見学や本部オフィスでの意見交換、グループホームの様子について掲載します。地域移行に向けた課題や学びなど、来週初めに掲載します。お楽しみに。
報告:DPI地域生活部会
こんな記事も読まれています
現在位置:ホーム > 新着情報 > 8月7日(木)社会福祉法人清心会 視察レポート①-40年以上にわたり取り組んできた地域福祉と地域移行支援の実践-