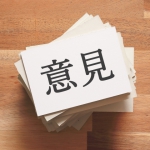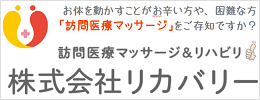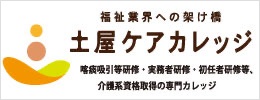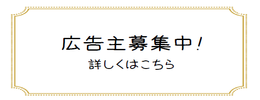「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書」を提出しました
2025年08月26日 要望・声明権利擁護障害者権利条約の完全実施

DPI日本会議は、2025年8月25日付で「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書」を提出しました。
本意見書は、国連障害者権利条約の理念に基づき、どんなに重い障害があっても必要な支援を受けながら地域で暮らし、自らの意思で決定できる社会を実現するため、成年後見制度の見直しが障害者の権利保障につながるものとなるよう求めるものです。
2025年8月25日
民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に対する意見書
(特定非営利活動法人)DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 平野みどり
はじめにー民法改正の中間試案への意見の前提
DPI(障害者インターナショナル)日本会議は、全国89の障害当事者団体から構成され、障害の種別を越えて障害のある人もない人も共に生きるインクルーシブな社会(共生社会)の実現に向けて活動を行っている団体です。国連経済社会理事会の特別諮問資格も保有し、国連での活動等、国際的活動も幅広く行っています。
中間試案に対する意見を述べる前に、まずは、今回の成年後見制度の見直しについて、民法改正ではない点も含めて改革の全般的な方向性についてDPIの考え方について述べます。
DPIの活動の根底にある理念は、社会参加の不利の原因は個人の機能障害ではなく社会環境にあるとする「障害の社会モデル」と、障害の社会モデルを基に障害のない人と実質的に平等な法制度を確立すべきとする「障害の人権モデル」に即した法制度の実現です。すなわち障害者権利条約(以下、権利条約)に規定されている障害者の権利の実現と保護となります。
今回の見直しは、2022年10月、国連障害者権利委員会より出された日本に対する総括所見を踏まえることが重要です。具体的には、必要な支援を受けながら、どんなに重い障害の有る人も障害のない人と「平等に」自らのことは自らが決めること(自己決定。条約上は自律)(権利条約第3条)、入所施設や病院ではなく地域で暮らせるインクルーシブ社会の実現(同第19条関連)、障害に基づく差別(障害に基づく区別・排除・制限/合理的配慮の不提供)の解消(同第5条他)、精神障害者の強制入院制度の廃止(同第14条)や障害の有無で分けられないインクルーシブ教育の実現(同第24条)などがあげられます。
どんなに障害が重くても、必要な支援を受けながら障害のない人と「ともに」生きることができる法制度の実現には、全ての人の法的能力(行為能力・権利能力)の承認とそれを支える支援体制の構築(同第12条他)が必要であり、今回の成年後見制度の見直し=民法改正は重要な一歩と考えます。
しかしながら、障害者の法的能力の承認と能力の行使のためには、今回の民法の改正以外にも、社会福祉制度の充実や消費者保護制度の拡充など、意思決定支援や権利侵害の防止体制を確立・強化していくことを同時並行で行うことが必要です。例えば、重度訪問介護の対象を拡大することや日常生活自立支援事業の拡充が求められます。また、障害者の権利を十分に理解した権利擁護のための人材を育成し、権利擁護のための公的な制度の創設なども必要です。
以上を前提として、以下、中間試案に対する意見を述べます。
中間試案への意見
■前注1 用語について
新制度における代理権や同意権等を付与される者につき、「保護者」という名称は適切ではないと考える。障害者の権利を擁護(保障)するための制度であるということ、非自発的入院制度を想起させる精神保健福祉法上の旧「保護者」制度や現行、医療保護入院を想起させることなどが理由である(本DPIの意見では「保護者」は中間試案の意で使用する)。
■第1の1(1)開始の要件及び効果(試案P.1-4)
この中では乙1案(試案P.2)に賛成する。
乙1案は、判断能力について「事理弁識能力が不十分であること」の場合と、「事理弁識能力を欠く常況」の二つを基本的に分けないで、請求権者の請求で保護者に代理権を与えるかどうかの必要性などを個別に裁判所が判断することで、最低限、権利条約が求める包括的代理権の撤廃に沿うものである。
甲案は現行の制度とあまり変わりがなく、乙2案は、保護者に類型的に取り消し権や代理権を与えることができるため、必要最低限の法的能力の制限とならない恐れが生じる。
例えば、入所施設の入所や退所について、障害当事者が希望する「入所したくない」や「退所したい」の意思が後見人によって尊重されない事例がDPIにも複数寄せられている。これは、一義的には後見人に期限のない包括的代理権を付与する現行制度上に問題があるからである。
■第1の1(1) 事理弁識能力、制限行為能力制度、審判の開始について
上記、乙1案においては、事理弁識能力制度、一律に法律行為を制限してしまう制限行為能力制度の見直しが求められる。
現行制度のように事理弁識能力の程度によって類型化するのではなく、あくまでも制度利用の前提として の判断能力の不十分さを認定することで十分である。
判断能力の有無や程度は本人や保護者(中間試案上の)の申し立てにより裁判所が認めた範囲においてのみ考慮されるべきであり、そうした法制度の整備が必要である。
よって、新たな制度に必要とされる判断能力の性質は現行の「事理弁識能力」と変わってくるので、改正民法における当該の用語も当然変えるべきである。
さらに、新たな判断能力については、現行法上の「精神上の障害により」という「障害」要件はなくすべきである。また、乙1案で改正が進められれば、現行制度の開始審判は必要なくなる。
DPIではかねてより、後見人、保佐人等による自己決定権の侵害の要因となってきた包括的代理権等の廃止、制限行為能力制度の廃止を求めてきた。今回の改正では、社会環境の整備状況を鑑みると代理権や同意権の付与はやむを得ない部分があるが、少なくとも、権利行使の重大な制限となっている本人が必要とする支援の内容とは関係ない法律行為についてまでも一律に行為能力を制限する現行制度は、必ず変えるべきである。
■第1の1(2) 本人の同意(試案P.4~7)
甲案に賛成する。ただし、同意権や代理権付与の例外要件は、本人の生命や身体、財産保全などに著しい不利益のある場合など、最終手段(ラストリゾート)として厳格に定めるべきである。
甲案は、後見などの保護を開始する審判(家庭裁判所の審議)や、保護者の同意がいるかどうか、代理権を保護者に与えるかどうかの審判を始めるときには、例外はおきつつも原則として本人の同意が必要、という案であり、これは障害者権利条約の要請である。
■第2の1(法定後見の終了)(試案P.8~11)
第1の1(1)で乙1案を採ることを前提に、(2)に賛成する。ただし、代理権 同意権等の付与の審判を取り消す場合、本人の同意を要件とすることは慎重な検討が必要である。
現行の成年後見制度では、本人が制度利用の終了を望んだり、後見などの保護の必要がなくなっても事実上終了できない。終了できる制度にすることがまずは大切である。
判断能力(現行の制限行為能力制度による)を要件とせず、本人が、福祉サービスなどを十分に受けることができるようになったなど、後見などの保護が必要なくなったと裁判所が認める場合は、本人や保護者などの請求権者の請求を検討し、代理権を与える審判(裁判所の決定)を取り消す制度とすべきである。
■第2の2(法定後見に関する期間)
法定後見についての期間は決めるべきであり、甲案には反対である。乙1案、乙2案共に、実質的に定期的に制度利用の見直しが行われる案であるが、DPIとしては、どちらかといえば、乙1案に賛成である(乙2案も排除するものではない)。
「期間」を決めるかどうかも終わることができる制度への変革の重要な点である。代理権や同意権の終了の期間を定め、制度利用の更新が必要だという保護者などの積極的な申立の上で、更新するかどうかを決める方法が、より、本人の当該法律行為の制限を必要最小限なものとすることができるのではないかと思われるためである。
必要がなくなってきているのに、本人を含む請求権者の自発的な代理権取り消しの申し立てだけでは、漫然と本人の代理を許す制度が継続してしまう恐れがあるためである。
■第3の2 保護者の解任(交代)等
乙2案に賛成する。
後見人等の自発的な辞任以外に、後見人等を交代させることができる制度が必要である。
欠格事由については、不正などの解任自由と欠格事由の連動については現行制度の維持が必要だが、新たな制度上で請求権者からの請求による解任全てが欠格事由と連動してしまうのは問題がある。請求権者については、現行法上の請求権者に加え、福祉3法における市町村申し立て案件については、市町村長も請求権者とすることが求められる。
DPIとしては、障害者本人の意向に反し後見人等が代理権などを行使し、施設に入所させたり、退所をさせない事例が複数寄せられていることから、例えば障害者本人の日常の状況をよく知る福祉事業者が解任等の請求に対して権利擁護の意味できちんと関与できる道筋が求められる。
以上、中間試案に対するDPIの意見とします。最後に、繰り返しになりますが、今回の民法改正による後見制度の改革が、障害者権利条約が求める理念や法制度に一歩でも近づくことができる改正となるよう、障害当事者団体として強く求めます。
今回の見直しで終わらないように、障害者権利条約が求める「代理決定から支援付き自己決定への転換」の実現のためのロードマップの作成と継続した検討・見直しを利用促進計画等にきちんと明記してください。
また、政府全体に対して、成年後見制度の見直しと並行して、福祉サービスの充実や見直しなども進めるよう、改めて強く求めます。
以上
▽民法(成年後見制度)見直しの中間試案に対する意見(ワード)