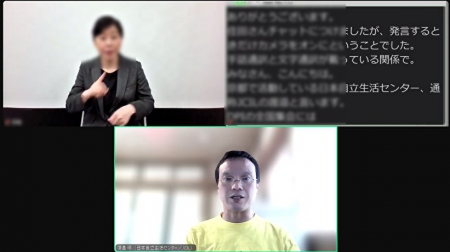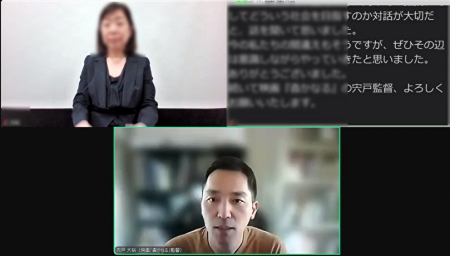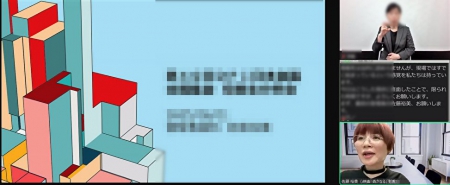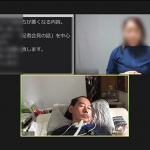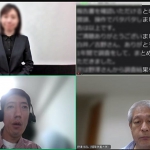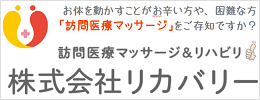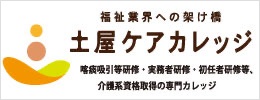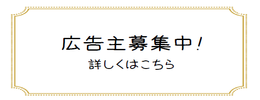【ポイントまとめ】尊厳ある生 安楽死・尊厳死・臓器提供 (=障害や難病、脳死などを理由を死期を早めること)をめぐる問題についてDPI全国集会「尊厳生分科会」報告・感想-
DPI全国集会「尊厳生分科会」について、報告を山崎 恵(DPI日本会議常任委員・DPI北海道ブロック会議事務局長)が、感想を参加者のレオ・ソーレンセンさん(CILふちゅう・ハンズ世田谷)が書いてくれましたので、ご紹介します!
こんなことが報告されました(ポイントまとめ)
(敬称略)
1.渡邉 琢(日本自立生活センター(JCIL))
- 安楽死・尊厳死の海外の動向と日本での議論について報告
- 「いかに生きるか」が語られないまま「いかに死ぬか」が先行して語られる現状に強い疑問を示し、障害者や難病当事者が地域で支援を受けながら生きる選択肢が十分に保障されていないことに警鐘を鳴らした
- さらに、知的障害者の臓器提供を可能にするガイドライン改正の動きについて、本人の明確な意思が確認できないまま「推定」によって進められることへの懸念を表明
2.岡本 直樹(DPI日本会議常任委員・CILふちゅう代表)
- 「臓器の移植に関する法律」の運用指針(ガイドライン)改正の動向について、問題点と背景を報告。特に、知的障害者の臓器提供において「本人の意思を丁寧に推定する」とされつつも、実質的には家族の同意で提供が進められる懸念を示す
- DPI日本会議として、ピープルファーストジャパンのメンバーとともに厚労省とヒアリングを重ねてきたこと、当事者の声を反映する取り組みを続けていることを共有
3.宍戸 大裕(映画「杳かなる」監督)
- 支援の欠如こそが人を追い詰め、生きづらさを生む
- 結果として安楽死が“解決策”とされる風潮が生まれている
- 映画を制作した背景に2020年に起きた京都ALS嘱託殺人事件がある
- この事件では、医師に懲役18年の判決が出されたものの、世間には「医師は悪くない」との声も強く、安楽死の法制化を求める動きが加速している
4.佐々木信行、小田島栄一、住田 理惠(ピープルファーストジャパン)
- 自分のことを他人が勝手に決めるのは納得できない(佐々木さん)
- 厚労省の説明が分かりづらく怒りを覚えた。なぜ知的障害者を狙うのか分からない(小田島さん)
- 旧優生保護法下での強制不妊手術や施設収容の経験が重なり、「また同じことが繰り返されるのではないかという不安がある(小田島さん)
- 理解し、仲間に伝え、意見として出す時間こそが合理的配慮である。その旨を要望書として厚労省に提出したが、その翌日に、何の反応もないままパブリックコメントが開始され、強い不信感と怒りになった(住田さん)
5.佐藤 裕美(映画「杳かなる」主演のお一人)
- 安楽死や尊厳死が「自己決定」として肯定される一方で、「どこで誰とどう生きるか」といった基本的な自己決定が日々踏みにじられている矛盾がある
- 生きるための支援が足りない社会で、『死にたい』という声ばかりが評価されるのは危険
- 私たちはどんな社会に生きたいのかという対話を終わりなく続けていく必要がある
詳細は下記報告をご覧ください。
去る5月31日(土)、6月1日(日)の2日間、「第40回DPI全国集会―国連・障害者権利委員会の最新動向と、日本が取り組むべき課題を共に考える2日間」がオンラインで開催され、6月1日(日)には尊厳生分科会テーマ「尊厳ある生――安楽死・尊厳死・臓器提供(=障害や難病、脳死などを理由に死期を早めること)をめぐる問題について」が行われました。
冒頭、JCILの渡邉さんより、安楽死・尊厳死の海外の動向と日本での議論について、制度化の流れに対する強い懸念が語られました。
自身の活動経験から、「いかに生きるか」を語る前に「いかに死ぬか」が語られてしまう現状に疑問を呈し、特に障害者や難病当事者が支援を受けながら地域で生きる選択肢が十分に保障されていないことに警鐘を鳴らしました。さらに、知的障害者の臓器提供を可能にするガイドライン改正の動きについても問題提起し、本人の明確な意思が確認できないまま「推定」によって提供が進められることへの強い懸念を示されました。
その後、尊厳生部会長の岡本から、昨年から動きのある「臓器の移植に関する法律」の運用指針(ガイドライン)改正の動向について、その問題点と背景を共有しました。
特に、知的障害者の臓器提供に関して「本人の意思を丁寧に推定する」とされながらも、実際には家族の同意によって進められてしまう可能性がある点に強い懸念を示しました。DPI日本会議としては、ピープルファーストジャパンの皆さんとともに厚生労働省とのヒアリングを重ねてきたこと、当事者の声を反映するための取り組みを続けていることについても報告されました。
また、ドキュメンタリー映画「杳かなる」の監督である宍戸さんからは、「支援の欠如こそが人を追い詰め、生きづらさを生む」「結果として安楽死が“解決策”とされる風潮が生まれている」と問題提起がされました。
この映画を制作した背景が2020年に起きた京都ALS嘱託殺人事件であること、医師に懲役18年の判決が出されたものの、世間には「医師は悪くない」との声も強く、安楽死の法制化を求める動きが加速していることも語られました。
後半では、ピープルファーストジャパンの佐々木さん、小田島さん、住田さんにも登壇いただき、佐々木さんは「自分のことを他人が勝手に決めるのは納得できない」と訴え、小田島さんは「厚労省の説明が分かりづらく怒りを覚えた。なぜ知的障害者を狙うのか分からない」との話がありました。さらに旧優生保護法下での強制不妊手術や施設収容の経験が重なり、「また同じことが繰り返されるのではないか」という不安があることも話されました。
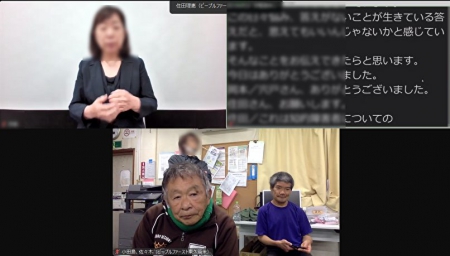
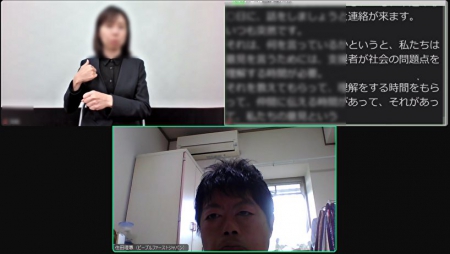
住田さんは、「理解し、仲間に伝え、意見として出す時間こそが合理的配慮である」と主張し、その旨を要望書として厚労省に提出したが、その翌日に、何の反応もないままパブリックコメントが開始され、強い不信感と怒りになった思いを話されました。
ドキュメンタリー映画「杳かなる」に出演されている佐藤さんは、安楽死や尊厳死が「自己決定」として肯定される一方で、「どこで誰とどう生きるか」といった基本的な自己決定が日々踏みにじられている矛盾を指摘されました。
さらに「生きるための支援が足りない社会で、『死にたい』という声ばかりが評価されるのは危険」だと訴え、「私たちはどんな社会に生きたいのかという対話を終わりなく続けていく必要がある」と話されました。
今回のガイドライン案では「拒否の意思が否定できない場合は、拒否があったとみなす」とされましたが、実際の現場でその原則がどこまで守られるのかは極めて不透明であると言わざるを得ません。
今後、制度を動かす行政・専門家・支援者には、障害当事者の「わからない」「時間が必要」という当たり前の声に真摯に耳を傾ける姿勢が求められています。そして、本人不在での議論ではなく、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という障害者権利条約のスローガンが守られる議論となることを期待します。
山崎 恵(DPI日本会議常任委員/DPI北海道ブロック会議事務局長)
参加者感想
安楽死の問題について、私自身はあまり安楽死について研究したことはありませんが、生きるということを認めることが大切だと思います。
人生を楽しめるということが重要です。障害者や利用者の意見を尊重し、憲法の観点からも考える必要があります。もし利用者が自分で苦しいから安楽死を希望するというのであれば理解できますが、基本的には慎重に考えるべき問題です。
昨年まで私が過ごしてきたアメリカでも安楽死(アシステッド・スーサイド)は実際に存在します。痛みが止まらないなどの条件がある場合に認められています。
アメリカの場合は、精神的に問題がないか、本当に自分の意思で決めているかを確認するルールがあります。医師は薬を処方できますが、実際に手伝うことはできません。患者が自宅で薬を服用し、心臓が止まった後に医師が死亡証明書を作成します。
この分科会で最後に話された方が、いろんな問題を抱えていても生きていてよかったと思うと言っていました。私も19歳から24歳くらいまでは辛い時期もありましたが、今は生きていてよかったと思う瞬間がたくさんあります。
安楽死を法的に考える際には、痛みを減らすことは大事ですが、人には目的があり、何かの理由で生きています。そう考えると、安楽死は安易に選択すべきではないと思います。
レオ・ソーレンセン(CILふちゅう・ハンズ世田谷)
こんな記事も読まれています
現在位置:ホーム > 新着情報 > 【ポイントまとめ】尊厳ある生 安楽死・尊厳死・臓器提供 (=障害や難病、脳死などを理由を死期を早めること)をめぐる問題についてDPI全国集会「尊厳生分科会」報告・感想-