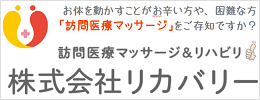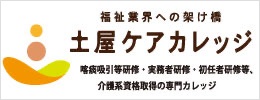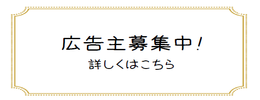第14回移動等円滑化評価会議が開催されました!小規模店舗のバリアフリー化検討へ
2025年09月22日 バリアフリー

9月17日に第14回移動等円滑化評価会議が開催されました。この会議は2018年のバリアフリー法改正で設けられた会議で、障害当事者等が参画し、定期的にバリアフリー化の進展状況を把握し、評価するものです。障害者団体、事業者団体、学識経験者、自治体等で構成されており、毎年2回開かれております。今回の議題は以下の4つでした。
- 第13回移動等円滑化評価会議における主なご意見と国土交通省等の対応状況について
- 国土交通省等におけるバリアフリー関係の取組事例について
- 当事者参画の取組事例の紹介
- その他
1. 第13回移動等円滑化評価会議における主なご意見と国土交通省等の対応状況について
前回出された意見に対し、国交省の対応状況が報告されました。鉄道に関してが非常に多く、中でも駅の無人化に関するものが多数ありました。他には、バス、タクシー、空港、高速道路、道路、運賃、交通結節点、信号機、観光、基本構想、心のバリアフリー、ICT、学校のバリアフリーに関する意見がまとめられておりました。
2. 国土交通省等におけるバリアフリー関係の取組事例について
全国10ヵ所に設けられている地域分科会の開催と内容、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会(今年の夏にまとまった第4次基本方針(整備目標))、公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会(ウエブサイト、授乳室での搾乳、トイレの環境整備等)、「建築設計標準」の見直し(6月に施行されたトイレ、客席、駐車場の新基準)、8月に取りまとまった新たな公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標(文科省)等が報告されました。
注目はテナント・小規模店舗のバリアフリー化に取り組むことが報告されたことです。小規模店舗はバリアフリー整備義務がなく、新しいお店でも車椅子では入れないものが続々と建設されており、これが日本の大きな課題です。DPIでは長年要望をしてきたのですが、ようやく取り組みが始まることになりました。住宅局からは、建築設計標準で例示しているが実効性のある対策を検討している、現在実態調査をしており、次回の建築設計標準フォローアップ会議で報告する、ということでした。
3. 当事者参画の取組事例の紹介
近畿地方整備局から、大阪・関西万博日本館のUDワークショップの報告がありました。学識経験者7名・障がい当事者25名、(施工段階) 学識経験者3名・障がい当事者22名が参画し、設計段階で6回、施工段階で4回開かれたということです。全体で182もの意見が出され、検証と反映が行われました。
建物入り口からの回廊はスロープですが、手すり、レールガイド、ラインガイドを設けることによって視覚障害者の誘導の役割も持たせる等の新しい取り組みがされておりました。トイレは様々な意見が出され、モックアップテストも行って検証し、整備したそうです。様々な整備が工夫されていました。
4. 主な意見
- 新幹線のWEB予約。使いづらくて使っていない。窓口に行っても1時間くらい待たされている。一般の方だとすぐ買えるのに。1時間以上経ってから連絡が来て取りに行くので改善してほしい。
- 飛行機の搭乗について。航空券を買うときに車椅子のサイズ、重さを伝えているが、カウンターで再度同じことを聞かれる。時間かかる。その場でもう一回測られたりして、時間が読めない。早く行ってもギリギリになる。事前に伝えたら、その場ですぐ搭乗できるようになるしてほしい。
- バスの乗車について。障害者用介助者用ICカードが出て便利になった。一部のバスは把握していない運転手さんがいる。割引になっているのに再度割引の操作をしたり、手帳の掲示を求められたりする(このカード発行する時に障害者手帳は見せている)。
- 基本構想はとても大切。2023年度末に334自治体で策定したとあるが、5年ごとの評価、見直しは行われているのか? →点検はしており、事務局は把握している。
- 障害者権利条約では「他の者との平等を基礎にして」という言葉がある。障害者は長い時間を有するとか不利益が多い。評価の軸の1つ。障害を持たない人との同等性。総点検で改善していくことが必要。
- 無人駅に関する意見がたくさん出ている。あえて、本当に駅の無人化はあり得るのか。安全性、サービス性で危惧がある。無人は最大のバリア。人の支えは最大のバリアフリー。ホームドアができるまでは有人で、モニターができるまでは人的対応等を含めて考えていかないと大きな問題になる。無人化を前提に議論されている。立ち止まりませんか。
- 音声情報の視覚化。好事例ではあるが、ツールがわからないと使用できない。スマホで利用できる音声認識アプリが進化し、生活に欠かせない。日常的に使用している。スマホがあれば全て解決しているように見えるが、スマホの費用負担ができない人は利用できない。
- 様々な障害特性の理解、対策が対応が議論されているが、支援を必要とする人がいる、重複障害もある。特定障害に留まらず、支援が必要な人への配慮、という考え方も必要。
- 高速道路の料金所に対する聞こえない人からの質問はモニター、筆談、職員に教育すると書いてある。情報の提供だけでなく、同時に障害者から質問できる方法が必要。
- ホームの段差と隙間。進展がないように思う。都心に行って電車に乗っているが、最近は進展がない。
5. DPIの意見
1. 新幹線・特急の車椅子席のWEB予約
各社取り組みを始めていただいているが、いまだにどの会社も不十分なままとなっている。介助者の席が一緒に予約・決済できない、障害者割引乗車券がWEBで決済できない等の問題がある。
先週、仕事で関西に行き、会議が長引いてしまい、予約していた新幹線に乗ることができなかった。車椅子席はWEBで予約・決済できないので、窓口でしか買うことができない。変更は予約した電車が出発する前に窓口に行かないとできない。今や障害のない人は窓口に行かずにスマホでいくらでも新幹線を変更できる。
車椅子使用者のみ著しく利便性が悪く、障害のない人と大きな格差がある。このようなことを改善するためには、WEBでの予約決済の改善が不可欠です。必要な要件は4つです。
- 車椅子席を予約・決済できる
- 介助者の席も一緒に予約・決済できる
- 障害者割引乗車券をWEBで決済できる
- 緑の窓口に行かずに全て完結できる
鉄道事業者にはこの4点を踏まえて改善をお願いします。国交省には各社が速やかに改善するように働きかけをお願いいたします。
2. 香害
香害(かおりがい/こうがい)は洗剤や柔軟剤、芳香剤や制汗シートなど多くの日用品に含まれる石油由来の合成香料などによって頭痛、めまい、吐き気、咳、全身倦怠感、皮膚のかゆみ、アレルギー症状など、多岐に渡りあらわれる健康被害のことです。
香害や化学物質過敏症で健康被害がでると、公共交通機関では途中下車や車両の変更(車いすでは車両の変更すらも降車駅までできません)、座席や車内や駅空間の合成香料が移香することにより帰宅後の入浴や洗濯を体調不良の中おこなうなどしています。
健康被害が出ると電車やバス、タクシー自体が使えなくなり、通学、通勤、通院など外出自体が困難になるケースも増えてきています。
公共交通機関の職員や利用者に向けた日用品の利用見直しをはかることと合わせて、現在ある消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省の5省庁作成の啓発ポスターの掲示は早急にお願いしたいです。また、公共交通機関に特化した課題啓発ポスターの作成も急務と考えます。ぜひ、ご検討いただきたい。
3. 小規模店舗のBF
テナント・小規模店舗のバリアフリー化に取り組んでいただけるということで、ありがとうございます。ただ、資料を読むと今回はテナントに限定されており、小規模店舗は次の段階となっているが、是非とも、分けることなく、一般の小規模店舗も併せて検討していただきたい。
新規の店舗でも段差があったり、椅子が固定式だったりして、入れない店が続々とできている。これはずっと改善できてない日本のバリアフリーの最大の課題です。ぜひ、新規のお店には段差を設けない、可動式の椅子にする等の最低限のバリアフリーの義務基準を設けていただきたいと思います。
まとめ
今回もたくさんの意見が出され、活発な会議でした。特に注目は小規模の店舗のバリアフリー化を検討すると住宅局から報告があったことと、大阪・関西万博日本館の取り組み報告でした。小規模店舗のバリアフリー化は、特別特定建築物の中のテナントを想定して考えているようですが、一般の店舗も新規店は最低限の基準を課すことが不可欠です。これを引き続き要望していきたいと思います。
大阪・関西万博日本館の取り組みは素晴らしいものでしたので、なぜそういう整備にしたのかという議論も含めて記録として残して欲しいと思います。今後、各地で当事者参画の施設整備が進められる時に、とても参考になると思います。
報告:佐藤聡(事務局長)