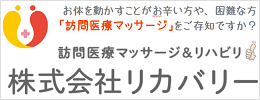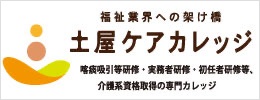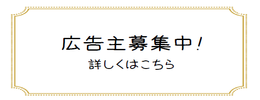HLPF2025参加報告:国連の現場から見えた“誰一人取り残さない”の現在地
2025年08月06日 地域生活権利擁護雇用労働、所得保障国際/海外活動防災・被災障害者支援

DPI日本会議事務局の笠柳です。2025年7月21日から24日まで、ニューヨークの国連本部にて開催された「国連ハイレベル政治フォーラム(High-Level Political Forum on Sustainable Development:HLPF)」に参加いたしました。
HLPFは、SDGs(持続可能な開発目標)の進捗状況を各国が報告・共有する場であり、経済社会理事会(ECOSOC)の下で毎年開催されている、国連における持続可能な開発に関する最も重要な会合の一つです。
各国政府のみならず、国際機関、市民社会、若者、企業、障害当事者団体など多様なステークホルダーが一堂に会し、現場の課題や優良事例を共有しながら、SDGs達成への道筋を模索します。
この度、朝日新聞社と岩佐教育文化財団による「HLPFサステナブルエンゲージメントツアー」の参加者に推薦いただき、この会議に参加できることになりました。DPI日本会議の一員として現地に赴き、SDGs(持続可能な開発目標)に関する各国・多様な関係者の議論や取り組みに触れたこの機会は、私にとって非常に貴重な経験となりました。
2025年は日本政府が自発的国家レビュー(VNR:Voluntary National Review)を提出する年であり、現地では政府代表による公式報告のほか、さまざまなサイドイベントや討論セッションが行われました。DPI日本会議としても、市民社会の側からVNRプロセスに参加し、障害分野の課題と提言を盛り込んだ市民レポートの作成に関わってきました。
このたびのHLPF参加を通じて、私たちが国内で抱えている課題が世界の流れとどうつながるのかを確認すると同時に、国際的な場で当事者の声を届けることの意義を改めて実感しました。以下に、参加した各セッションについて概要になりますが報告いたします。
自閉スペクトラム症に取り組む個人、家族、地域社会に対する、持続可能で包摂的、かつ科学的・証拠に基づいた解決策
英語タイトル:Sustainable, Inclusive, Science-and Evidence-based Solutions to Individuals, Families and Communities Dealing with Autism Spectrum Disorder

このセッションでは、自閉スペクトラム症(ASD)のある人々やその家族、地域社会を支える支援体制の現状と課題、そして今後のあるべき姿について議論が行われました。WHOのオーベルマイヤー博士の司会のもと、ASDがSDGsのうち保健(SDG3)、教育(SDG4)、雇用(SDG8)、パートナーシップ(SDG17)と密接に関係していることが強調されました。
ブータンのドゥルジ大使は、多くのASDのある人々が未診断のまま支援にアクセスできず、家族も孤立しているという発展途上国の課題を紹介しました。ウガンダのカベンゲ氏は、自身の姪が重度の障害を持っていることを語り、地方では相談機関がないため、無料電話相談などの草の根支援が重要であると述べました。
さらに、インドやアメリカからは、ABA(応用行動分析)などの科学的根拠に基づいた支援の重要性、また高等教育機関での神経多様性を尊重した制度設計の取り組みが紹介されました。特にアメリカの大学では、ASDのある学生向けに専門スタッフによる就学支援制度を構築している事例も示され、多様な現場からの実践が共有されました。
一般討論(General Debate)

本セッションでは、70を超える国・地域の代表が、3分という限られた時間で自国のSDGsの進捗や課題、そして国際連携への姿勢をスピーチしました。議場では「SDGsがオフ・ザ・トラックにある(Off the Track)」という表現が何度も繰り返され、各国が進捗の遅れに共通の危機感を抱いていることが感じられました。
中でも、パキスタンやナイジェリアなどの代表は、気候変動や貧困の二重苦の中でも希望を持って取り組んでいる現状を強調し、先進国に対して財政的・技術的な支援を求める声が目立ちました。意外だったのは、AIやデジタル技術への具体的な言及が少なかったことで、各国の技術導入の進度や注目度にギャップがあることを感じました。
防災によって持続可能な経済成長を確保するための戦略
英語タイトル:Strategies to Ensure Sustainable Economic Growth Through Disaster Risk Reduction

気候変動の影響によって災害の頻度や被害の規模が拡大するなか、各国の経済・社会のレジリエンスをどのように高めていくべきかについて、防災(Disaster Risk Reduction: DRR)の視点から活発な議論が交わされました。
災害による世界の経済損失は、2015年から2021年の間で年間平均3,300億ドルに上るとされており、これを抑制するには防災への投資が不可欠であるという共通認識が示されました。防災はSDGsの目標8(働きがいのある成長)や目標5(ジェンダー平等)とも密接に関わることから、各国の政策・制度にDRRを主流化していく必要性が強調されました。
イベントの冒頭では、日本の宮路拓馬外務副大臣、UNDRRのカマル・キショール長官(ビデオ登壇)、UNDPの野田翔子アシスタント事務総長、タイ外務省のパイサン・ルパニチャキット次官がそれぞれ開会挨拶を行い、防災分野への継続的な投資と国際協力の重要性を訴えました。
続くパネルディスカッションには、UNDP、仙台市、メキシコ防災庁、JICA、日本商工会議所青年部、セーブ・ザ・チルドレンUSA、若手気候活動家など、多様な立場の登壇者が参加しました。
仙台市からは、東日本大震災後に策定した復興都市計画の内容や、市民と連携した防災訓練の取り組みが紹介され、住民主体のレジリエンス強化の実践が注目されました。JICAは、開発途上国での防災リーダーの育成や、地域社会を巻き込んだ教育プログラムの成功事例を発表。現地に根ざした支援の重要性と、日本が果たす国際的役割について具体的なビジョンが示されました。
本セッションを通じて、防災は単なる危機対応ではなく、経済の持続可能性や社会の包摂性を高める戦略的投資であるとの認識が共有されました。
■「災害時の障害者支援も含めた防災計画」の必要性について発言をしました
私はこのセッションの最後の質疑応答の時間に、一言発言の機会をいただきました。2011年の東日本大震災では、障害者の死亡率が一般の2倍以上にのぼり、多くの方々がバリアフリーでない避難所に避難できず、また避難所にとどまることすらできませんでした。
防災と経済成長の関連が議論される中、「障害」の視点が完全に抜け落ちていたことに強い違和感を覚え、限られた時間の中で詳細まで語ることはできませんでしたが、これまで支援活動を続けてきた方々への敬意を込めて、「災害時の障害者支援も含めた防災計画の必要性」を国連の場で伝えることができました。
発言後には、参加者から共感や関心の声も寄せられ、障害と防災の交差点に光を当てる一歩となったと感じています。
日本の自発的国家レビュー(VNR)報告

日本政府によるVNR(自発的国家レビュー)では、宮路外務副大臣が、「マルチステークホルダーの関与」「成長と持続可能性の両立」「知の国際交流」の3つを柱に据え、報告を行いました。バリアフリーに関連する部分では、NPO法人ウィーログの織田友理子代表が登壇し、ご自身の経験や活動を交えて、「誰もがあきらめない社会」の実現に向けた熱意あふれるスピーチを行いました。
さらに、ブルガリアからの「高齢化への対応」、タイからの「災害リスク軽減策」、イギリスからの「気候変動とエネルギー政策」に関する質問をはじめ、多くの国からの問いかけに対して、日本政府は具体例を挙げながら丁寧に回答しておりました。たとえばプラスチック循環法については、「製品ごとではなく素材ベースで規制を行うことで、すべての関係者が関与できる制度に転換した」と明言していました。
しかしながら、「障害」に関する記載や説明は極めて限定的でした。現在の日本では、障害のある人々が望む地域で生活するための支援が依然として不十分であり、多くの人が施設に隔離されるような状況が続いています。また、インクルーシブ教育の実現にも多くの課題が残されており、障害のある子どもたちは分離された教育環境に置かれているのが実情です。
これらの課題については、2022年に国連障害者権利委員会から日本政府に対して厳しく勧告が出されていますが、残念ながらその多くは未だ実行に移されていません。こうした深刻な状況が、今回のVNR報告の中で十分に触れられていなかったことは、非常に残念に感じました。
今回の現地参加を通じて得られた経験と学びを活かし、引き続き国内外にこうした課題の実態を発信していきます。そして、国連のレビュー文書などにも実情が正確に反映されるよう働きかけていきます。とりわけ、障害者権利条約(CRPD)とSDGsを両輪として、日本における障害者政策の真の変革を推進していく必要があると、改めて強く感じています。
インクルーシブで持続可能な雇用に関するセッション
英語タイトル:Inclusive and Sustainable Jobs: How to Ensure Everyone Can Participate in the Labour Market

このセッションでは、SDG8を基盤に、特に障害者、女性、若者、高齢者、先住民族が労働市場から排除されず、尊厳をもって働ける社会の実現について多角的な議論が行われました。
カナダ政府のPatty Hajdu大臣は、社会的孤立を防ぐ政策と起業支援について述べ、フィンランド環境省のAnnika Lindblom氏は、子どものケアと教育支援が女性の社会参加に重要だと強調しました。UNEPのLigia Noronha氏は、グリーン経済が持続可能な雇用を生み出す可能性を提示しました。
障害者に関しては、カナダ自閉症支援団体のSiyu(スーユ)・チェン氏が、合理的配慮を前提とした職場設計の必要性と、多セクター協働による包括的支援の重要性を訴えました。私は会場で彼女と直接言葉を交わす機会を得て、今後の連携に期待を寄せています。
また、ナイジェリアNGO代表のOluseyi Oyebisi氏は、資金不足が続くアフリカのNGOにおける雇用創出の困難さを率直に語り、持続可能な雇用確保には政府・市民社会・民間の三者による連携が不可欠であると述べていました。
これらのセッションはそれぞれ異なる切り口からSDGsを捉えながらも、「包摂(インクルージョン)」という共通の視点が常に語られていたことが、強く印象に残っています。
国際会議の場における当事者の“存在感”
今回のフォーラムでは、日本を含む多くの国のSDGsに関する進捗報告が行われました。しかしながら、「障害」に関する言及は驚くほど少なく、会場設備も完全なバリアフリーとは言い難い状況でした。車椅子利用者用の音声設備が不足していたり、字幕が途中で途切れたりするなど、情報アクセスの面で多くの課題が見られました。
こうした現実を前に、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」が、障害者にはまだ十分に届いていないことを強く実感しました。そうした中で、国際会議の場において、障害のある当事者として発言の機会を得られたことは、大きな意義がありました。さらに、多くの国際的な障害当事者の方々とも直接つながることができ、今後の活動にもつながる実りある出会いの場となりました。
最後に-国際連携を見据えたこれからの取り組み-
今回の参加を通じて、国際社会におけるSDGs達成の歩みが、いかに厳しいものであるかを肌で感じました。会議では「オフ・ザ・トラック(目標達成の道筋から外れている)」という表現が繰り返し使われ、多くの国が課題を抱えながらも、協力し合い前進しようとする強い意志が語られていたのが印象的でした。
一方で、今回のVNR報告において、「障害」に関する記載や説明が極めて限定的であったことには、大きな課題を感じました。現在の日本では、障害のある人々が望む地域で生活するための支援が依然として不十分であり、多くの人が施設に隔離されるような状況が続いています。また、インクルーシブ教育の実現にも多くの課題が残されており、障害のある子どもたちは分離された教育環境に置かれているのが実情です。
こうした課題については、2022年に国連障害者権利委員会から日本政府に対して厳しい勧告が出されていますが、残念ながらその多くは未だ実行に移されていません。このような深刻な状況が、国際的な報告の場で十分に取り上げられなかったことは、非常に残念であり、引き続き改善を訴えていく必要があると強く感じています。
今回の現地参加を通じて得られた経験と学びを活かし、こうした課題の実態を国内外に発信していきます。また、国連のレビュー文書などにも、現場の実情が正確に反映されるよう働きかけていきます。そして、障害者権利条約(CRPD)とSDGsを両輪として、活動を継続してまいります。
「地域で暮らしたい」という当たり前の願いが、誰にとっても実現できる社会の実現を目指して、今後も国際的な連携を深めながら取り組みを継続してまいります。
最後に、このような貴重な機会をいただいた朝日新聞社および岩佐教育文化財団の皆さまに、心より感謝申し上げます。
報告:笠柳 大輔(事務局長補佐)