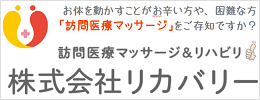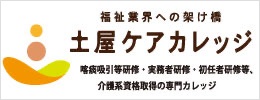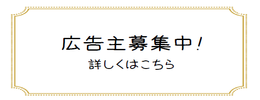「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2025年8月号)
2025年08月01日 イベント地域生活バリアフリー権利擁護障害女性国際/海外活動
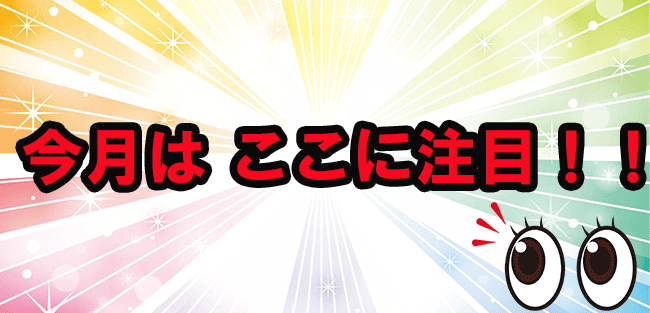 現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2025年8月号」をお届けします。
現在の国の動き、障害者運動に何が起きようとしているのか、情勢を追いかけるためにもってこいの「ここに注目!2025年8月号」をお届けします。
今月の注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなど各分野でまとめてお届けします。
これを読めば一目瞭然!
凡例:◎=大注目! 〇=注目! △=よかったら見て
クリックすると各分野に移動します
地域生活
◎大注目!
日程未定:障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
<ワンポイント解説>
6月25日(水)に第2回「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」が開催されました。次回の開催予定日はまだ決まっていませんが、9月には中間とりまとめとなるスケジュールが示されています。
脱施設化、地域移行の促進に向けたとても重要な検討会ですので、検討会資料などぜひご参照ください。
以下のリンク先に検討会のページがありますので、過去の資料や今後の開催案内など確認する場合はこちらのページをチェックしてみてください。
▽障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(外部リンク:厚生労働省)
バリアフリー
○注目!
日程未定:2027年国際園芸博覧会 第1回GREEN×EXPOアクセシビリティに関する取組
<ワンポイント解説>
2027年に横浜市内で開かれる国際園芸博に向けて、昨年度はアクセシビリティ・ガイドラインを策定しました。今年度も開催に向けてアクセシビリティの委員会が持たれ議論されるようです。第1回は8月に開催されるようです。
▽2027年国際園芸博覧会アクセシビリティ・ガイドライン(外部リンク:2027年国際園芸博覧会)(PDF)
教育
◎大注目!
第22回 障害児を普通学校へ・全国連絡会 全国交流集会 in埼玉~出会えないのはなぜ?
■とき:2025年11月22日(土)・23日(日)
22日(土)13:00~全体会、16:00~分科会、18:30~懇親会
23日(日)9:00~分科会、11:15~全体会
■ところ:岩槻駅東口コミュニティセンター(〒339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町3丁目1−1 WATSU西館)
■参加費:2日間3,000円、1日のみ 2,000円(ズーム参加同額)、懇親会4,000円(先着80名のみ)
■申し込み締切:9月30日(火)
▽以下のウェブフォームからお申し込みください。
お申込みフォーム
◇お問い合わせ:donokomo1987☆yahoo.co.jp(☆→@)、ファックス 048‐942‐7543 (タケサコ)
2年に1度の全国交流集会(DPI後援)です。今年は埼玉で行われます。分科会は、
- 「まずは保育園、幼稚園、学校で会いましょう」、
- 「みんなが居られる学校とは」、
- 「「合理的配慮」を問い直す」、
- 「共に学ぶ と、共に働く の間を考える」
以上の4つです。開催は11月ですが「懇親会」は先着順ですので、ご希望の方はお早くお申し込みいただくのがいいと思います。
国際
○注目!
WHOが障害者健康公平性イニシアティブを立ち上げました
<ワンポイント解説>
WHOは、6月10日(火)の第18回障害者権利条約締約国会議で13億人以上の障害者の健康の公平性を促進するための「障害者健康公平性イニシアティブ」を発表しました。
政府、医療機関、地域社会がケアの障壁に対処し、包括的な政策を促進し、障害と健康に関するデータと研究を強化するよう導くことを目的としています。
WHO障害テクニカルリーダーであるダリル・バレット氏は「医療制度は目的に合わず、サービスは包括的でアクセスしやすいものでなければならない」と言っています。
その4つの戦略的柱は
- 障害者とその団体によるリーダーシップ
- 障害インクルーシブな健康の政治的優先順位付け
- インクルーシブな医療システムとサービス提供
- データとエビデンスの強化
です。
私たちもブラジルで実施しようとしている「インクルーシブな保健システムの構築プロジェクト」と同じ流れに沿った宣言として歓迎する一方、世界の人口の高齢化の影響もあり、ここ数年の国際舞台の流れに沿って「障害者のケア」という表現が使われ始めていることに注意しなければなりません。
「ケア」では障害者の自立生活での自己管理、自己決定がないがしろにされ、「介助」という用語を根付かせてきた運動の精神が否定されてしまいます。
▽Partners unite to launch WHO Disability Health Equity(外部リンク:WHO)(英語)
○注目!
「エコ不安」という表現をユニセフが使いはじめました
<ワンポイント解説>
気候変動は、世界の障害者、特に途上国の障害者に大きな影響を与えています。物理的な面だけでなく、子どもたちやその他の弱者のメンタルヘルスにも影響を与えています。
予測不可能な地球の変化の規模とスピード、世界をより安全な場所にするため模索を重ねている行動がその背景にあります。
地球上で起きている変化に対する不安感は、政府など何かをする力を持つ人々がしばしば逆のことをしているのではないかという危惧によってさらに悪化します。
障害者団体などのコミュニティの一員になり感情や考えを共有し、事態の悪化を食い止めるためにできることをする勇気と決意を見出すべきです。
▽What is eco-anxiety?(外部リンク:UNICEF)(英語)
〇注目!
【セミナー】8/27(水)JICA社会保障・障害と開発分野プラットフォーム主催セミナー「アジアの未来を築く:障害者自立生活運動のリーダーたちの挑戦」(主催:JICA)
<概要>
アジアの6カ国(パキスタン、ネパール、カンボジア、台湾、モンゴル、ベトナム)から障害者の自立生活を牽引するリーダーをお招きしてのセミナーを開催いたします。
このセミナーでは、各国のリーダーたちが障害者の自立生活を実現するためにどのように取り組んできたか、何に力を入れているか、そして直面している課題についてお話いただきます。
リーダーたちの経験と知識を共有することで、地域や国を超えた協力の可能性を探り、障害者の自立生活をさらに推進するための道筋を見つけることを目指します。
この貴重な機会を通じて、障害者の自立生活に関する理解を深め、共に未来を築くための一歩を踏み出しましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
■日時:2025年8月27日(水)14:30~16:15(日本時間)
■開催方法:対面(JICA麹町本部:所在地 〒102‐0084 東京都千代田区二番町5‐25 二番町センタービル)とオンラインのハイブリッド開催
■情報保障:手話通訳、PC文字通訳、事前の電子データ提供等の対応をいたしますので、ご希望の場合は、8月13日(水)までに以下の参加申込フォームにその旨をご登録下さい。
※当日は資料の印刷配布を行いませんので、予めご了承願います。
▽申し込みは以下のフォームからお願いします。(8/26(火)締切)
▽DPIホームページでもご案内しています。
【セミナーのご案内】8/27(水)JICA社会保障・障害と開発分野プラットフォーム主催セミナー「アジアの未来を築く:障害者自立生活運動のリーダーたちの挑戦」(主催:JICA)
△よかったらみて
英語の絵本を見ると、ポジティブに障害を子どもに伝えています
1) Susan Laughs, by Jeanne Willis, and illustrated by Tony Ross
スーザンは笑い、歌い、父と一緒に泳いだり、学校で頑張ったり、友達と遊んだり、馬に乗ったり。忙しくて幸せな少女のイラストは、スーザンが車椅子を使用していることを物語の終わりで明らかにします。
▽Susan Laughs(外部リンク:macmillan(出版社。リンク先に表紙イラストなどが掲載されています)(英語)
2) Come over to my house、by Eliza Hull and Sally Rippin
「わたしの家に来て」は、聴覚障害のある子どもや親の家庭生活を探求する豪華な絵本です。素敵な韻を踏む英語の文章も多いです。
遊びに来てください、案内してあげるよ、一日中滞在してもいいよ。ブランコセットでブランコをしたり、プールで水しぶきを上げようとしたり、友達を遊びに誘う様子が描かれています。
▽Come Over To My House (外部リンク:Daniel Gray-Barnett(作家のウェブサイト。リンク先に表紙イラストなどが掲載されています)(英語)
障害女性
<ワンポイント解説>
障害者権利条約委員会は、条約が締約国で完全に実施されるよう締約国ごとの定期的な審査を実施しています。日本は2022年に建設的対話が行われ、同年9月に総括所見が出されました。
それとは別に、締約国すべてに出される文書として、例えば一般的意見(解説書のようなもの)とガイドラインがあります。
今回、障害女性と少女に関するガイドライン策定にあたり、委員会から意見を求められています。ガイドラインは一般的意見より政策や措置の実施に影響があると考えられます。
◎大注目!
障害のある女性と少女に対する複合的で交差的な差別への取り組みに関するガイドライン草案
(下記は、国連サイトの英文を翻訳したIMADR(反差別国際運動)の訳を参考に、DPIでまとめたものです)
障害のある女性と少女への複合的で交差的な形態の差別の対処に関するガイドライン草案に対して、書面の提出を呼びかける障害者権利委員会 ■目的締約国やその他の義務者を、障害のある女性と少女に対する複合的で交差的な形態の差別に対処するなかで生じる実施上のギャップに対処し、好事例のデータを収集できるように指導すること ■背景2009 年の設置以来、障害者権利委員会は条約締約国から提出された 150 以上の報告書を検討してきました。そのなかで、委員会は、第5 条(平等および無差別)、第6 条(障害のある女性)および第16 条(搾取、暴力および虐待からの自由)の国内実施において、以下のギャップを特定しました:
■目的委員会は、法律、政策、実施における障害のある女性と少女に対する複合的で交差的な形態の差別に対処するためのガイドラインの策定を決定した。その目的は、締約国やその他の義務者を、障害のある女性と少女に対する複合的で交差的な形態の差別に対処するなかで生じる実施上のギャップに対処し、好事例のデータを収集できるように指導することである。 ■主要な質問と求められるインプット/コメントの種類委員会は、関係するすべてのステークホルダーに対し、ガイドラインの内容について書面による意見の提供を呼びかけます。以下のトピックの中から1つあるいはそれ以上のトピックに関して書面による意見を提出してください。
■その他の事項
|
優生保護法と優生思想
<ワンポイント解説>
旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議(定期協議)の下に設置された3つの作業部会の委員がほぼ決定しました。すでに開始されている「被害者の被害回復」第一作業部会にも、優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)構成団体の中から新たなメンバーが加わり、8月1日(金)14:30~に開催されます。
また「人権教育・啓発」第二作業部会にはDPIから平野議長と崔議長補佐が、「偏見差別の根絶」第三作業部会には佐藤事務局長と白井事務局次長が、今後開始される各部会に参画することとなりました。
そして旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(補償法)で明記された検証について、主体である国会と委託先である日弁連法務研究財団との間で委託契約が締結され、いよいよ検証会議が9月よりスタートする見込みとなっています。
今後の動きは随時報告していきますので、引き続きご注目ください!
以上
こんな記事も読まれています
現在位置:ホーム > 新着情報 > 「今月はここに注目!!」各分野での注目すべき検討会・パブリックコメント・裁判・イベント・動きなどまとめてお届け!(2025年8月号)